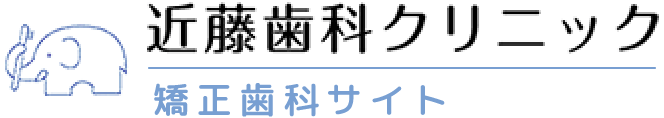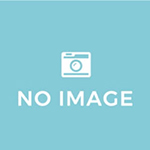矯正治療をされた方

もくじ
矯正治療をされた方
矯正治療をされた方、矯正治療終了時にはきれいに並んでいた歯がしばらく時間が経つとまた、重なりが目立ってきて歯並びが悪くなってしまった、という経験はありませんか?
矯正後、歯並びがまた乱れてくることを“矯正後の後戻り現象”と言います。
原因は以下考えられます。
- ①矯正時、歯を動かすことだけを重視し、口周りの機能を変えていくことをしなかった。
- ②普段、口呼吸をしている。または、よく口を開いている。
- ③鼻づまりがある。(花粉症などの季節的、または慢性的)
- ④しゃべるとき舌が出る
- ⑤姿勢が悪い
- ⑥あまり歩かない(過度の運動もマイナスですが)
- ⑦体調の変動が大きい。
これらは、一見、歯並びとは関係ないように思われますが、実は密接な関係があるのです。
歯並び、噛み合わせは、噛み方、飲み込み方などの口周りの機能、生活習慣、体質などの結果、その人に合った形態に作られていくのです。
そして、年齢、体質とともに変化もします。
ですから、体の中で、“歯並び”だけ変えよう、と思っても難しいのです。
では、後戻りが起こりにくいようにするには、どうしたらいいのでしょうか?
以下、立川の近藤歯科クリニックでは以下、矯正治療の患者さんにお話ししています。
矯正治療後の後戻りを少なくするには

- 1. 口呼吸から鼻呼吸へ変えていく(鼻づまりの人は耳鼻科の受診を勧める)
- 2. 舌を口蓋につけるトレーニング(ポッピングなど)
- 3. 姿勢を悪くしないように(椅子の座り方、眠るときなど)
- 4. 噛み方の改善
- 5. 適度に歩くこと
- 6. 生活習慣の改善
以上が主なことですが、その人によってそれぞれ課題があります
歯を抜かない矯正治療が後戻りの防止に寄与する?

咬み合わせの安定が後戻りを防ぐ鍵
近藤歯科クリニックでは、永久歯を抜かない矯正治療を重視しています。
なぜなら、矯正後の歯並びは“咬み合わせ”によって維持されているためです
咬み合わせがしっかりしていれば、食事の際に上下の歯が自然に支え合い、歯列が安定します。
一方で、永久歯を4本以上抜いてしまうと、咀嚼に必要な歯の本数が減り、咬む機能が低下しやすくなります。
この機能の低下は、矯正後に歯が元の位置に戻ろうとする「後戻り」を引き起こす原因となります。
歯にかかる力のバランスが重要
抜歯矯正では、スペースを確保するために歯を後方や内側に大きく動かすことが多く、その分、歯を支える骨や歯茎への負担も大きくなります。
これに対して、抜かない矯正では歯列全体をバランスよく拡大し、自然な位置に歯を配列するため、歯や歯茎へのストレスが少なく、長期的に安定しやすい特徴があります。
歯に無理な力をかけずに機能的な位置に配列することで、矯正後も後戻りが起こりにくくなります。
“よく噛める”ことが最大の予防策
矯正後に「よく噛める」という状態は、咬合による歯列の安定だけでなく、顎の筋肉や舌の動きなども自然に機能する環境を作ります。
このような機能的な口腔内の環境こそが、見た目だけではなく、長期的な後戻り防止にもつながるのです。
近藤歯科クリニックでは、こうした「抜かない歯医者」としての治療方針により、後戻りしにくく、しっかり噛める矯正をめざしています。
詳細については「歯を抜かない矯正治療」のページをご覧ください。
まとめ
矯正治療は、歯を動かすことも必要ですが、それと同時に、口周りの機能回復、正しい舌の動き、適正な噛み方(咀嚼運動)、正しい姿勢の維持、生活習慣の改善が大事です。
立川の近藤歯科クリニックでは、矯正治療開始時期から、それらを治療時に毎回、患者さんにご説明しています。